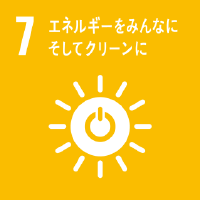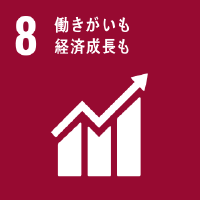電気自動車の普及に欠かせない、電池診断技術の開発。
これから電気自動車が普及していくにあたり、課題となるのが電池の再利用です。現在は月数万ほどの電池が販売店などから回収されており、そこから簡易診断、スクリーニング、精密検査を行い、約20%の電池が再利用されています。ただ、この診断には丸1日かかってしまうところを、今回5分で90%の精度を実現する簡易診断器を開発。しかし、実際にはその何倍もの電池が必要なため、民間に流れている分をトヨタ診断電池として活用できる仕組みづくりを目指しています。
試行錯誤を重ねた独自の仕組みで、世界トップレベルの診断技術を実現。
もともと新しい電池の評価に関わっていました。新品の電池は材料や工法さえ決めれば性能が決まります。一方で使用済みの電池は電池ごとに劣化具合が異なり、ひとつひとつ診断が必要です。しかし、これからのビジネスを考えると、どうしても必要な技術なので、各部門に話を聞きに行き、電池の入荷量や利益が出る仕組みを調べて提案しました。機器の開発に関しては、世の中に関連する技術がなかったので、すべて一から勉強しながら行いました。そして、充電と放電の際の電圧の上がり下がりをグラフ化して、その面積の変化から劣化を診断するアルゴリズムを開発。車ごと診断する技術もあり、世界トップレベルの診断技術を誇ります。
技術開発がゴールではなく、目指すのは電池の循環する仕組みづくり。
ここまで2年くらいかかっていますが、現在は民間企業とも協力体制を構築し、さらにデータを集めています。そして、その協力のもとでトヨタに戻ってこない電池にも認定制度をつくることを目指しています。これからの取り組みのなかで、資源の有効活用を実現していきたいです。また、車のまま電池を診断できることで、ディ ーラーで電池の交換時期を明確にできることや、中古の電気自動車の値付けも正確に行うことができます。
※掲載内容はSDGs TS report 2022作成時の情報です